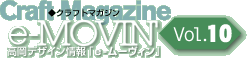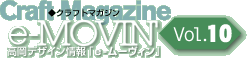| そして地元高岡からは、伝統的工芸品をつくっている銅器の竹中製作所と漆器の高岡漆器の社長が出席された。高岡銅器は昭和二十年代までは、火鉢、瓶かけなどを中心に床の間に置く七福神や恵比寿・大黒などを生産し、当時は問屋が今日でいうコンテナで三台分とか五台分をまとめて買っていったほどであった。その後、高岡銅器は美術装飾品に比重が移り、アメリカを中心とした輸出が堅調に推移。竹中時造さん自身もワシントンで飛び込み営業をし、その場で商談がまとまるケースがあったという。
ところが現在はアメリカ向け輸出はゼロになっている。以前、取引きしていた社長は「一ドル二〇〇円になったら売れる。三〇〇円なら飛ぶように売れるだろう」と竹中さんに答えるそうだ。
 「いいものをつくっても、安くなければいけない。安くするのがデザインではないかと思う。当社も社内にデザイナーを置き、また嘱託のデザイナーと協力して商品開発をしているが、製造工程の改革やデザインの角度からコストダウンが図れないかといつも検討している。そういうなかで、平成十二年に無印良品から商談があり、地元のメーカー数社と打ち合わせをする機会がありました。当社ではその前年から、黒川雅之さんデザインの「ジャポニズム」の商品化を進めていましたが、先方はそれを目に止めてくれたようです。ところが話し合いを進めても、値段が折り合わない。通常の三分の一くらいで納めなければならないので、最初の商談に出席していた常務は断りました。他の会社も断ったようです。 「いいものをつくっても、安くなければいけない。安くするのがデザインではないかと思う。当社も社内にデザイナーを置き、また嘱託のデザイナーと協力して商品開発をしているが、製造工程の改革やデザインの角度からコストダウンが図れないかといつも検討している。そういうなかで、平成十二年に無印良品から商談があり、地元のメーカー数社と打ち合わせをする機会がありました。当社ではその前年から、黒川雅之さんデザインの「ジャポニズム」の商品化を進めていましたが、先方はそれを目に止めてくれたようです。ところが話し合いを進めても、値段が折り合わない。通常の三分の一くらいで納めなければならないので、最初の商談に出席していた常務は断りました。他の会社も断ったようです。
でも私は、これはチャンスだと思った。国内の製造・加工の現場を組み合わせて調整したところ、コストダウンできたのです。それで、無印良品さんに再度話を持ちかけたら二五万個の注文をいただきました。この商品はヨーロッパで販売していて、結構売れているから、追加があるかもしれないという。今回の商談では、もちろんデザインも大事な要素だったのでしょうが、価格が合ったことが大きな問題だったと思う。日本はやはり輸出でマーケットが拡大できるよう、コストダウンを図らなければならない」と強調された。
銅器をめぐる環境は年々厳しいものになっているが、竹中製作所では池田満寿夫さん、岡本太郎さん、松永真さんなどの作品をブロンズにしたり、金属加工の技術を応用して、門扉・フェンスなどのエクステリアも生産。昨年は、インターネットによる商品の販売にも踏み切り、「予想していたより、売れている」と新しい販売方法にも期待を寄せていた。
 高岡の漆器業界も、厳しい環境に置かれている。そういうなかでも高岡漆器の国本吉隆さんはクラフトショップとギャラリーを併設した新店舗を昨年五月にオープン。メーカー自らが販路を拡大し、活路を見い出そうとする意気込みがうかがわれる。 高岡の漆器業界も、厳しい環境に置かれている。そういうなかでも高岡漆器の国本吉隆さんはクラフトショップとギャラリーを併設した新店舗を昨年五月にオープン。メーカー自らが販路を拡大し、活路を見い出そうとする意気込みがうかがわれる。
「高岡市には全国のクラフトマンが注目するクラフトコンペがあります。毎回二〇〇〇点あまりの作品が応募され、全国から多くのクラフトマンが高岡にこられるけど、展示期間が終わってしまうと、もう見ることができない。だったら通年でそれらを展示販売し、合わせて市場や価格の動向、またお客さんの声を聞く場として小売の現場を自分たちでも持とうと考え始めました。
当社も漆器製品のデザイン開発は積極的にやってきました。しかし工芸品は性能などで商品価値が計れず、マーケットはぼんやりしている。ですから、金科玉条のようにやってきた新商品の開発も、ほとんどうまくいってません。商品の大半は都市部のデパートで販売していますが、秋の商品の入れ換えの時期がくると頭が痛い。周りの漆器や食器と違和感があるというので採用されないことがある。また、徐々に売れ始めてきても商品を入れ換えなければならないことが多い。漆器は金属加工のように金型がないため形を変えやすいというメリットがありますが、売れ筋の商品が出るといろんな産地で類似品をつくって、商品の寿命を短くしているようなところもあるのではないか」
国本さんは、漆器業界の事情を踏まえながら、自らがショップを持つことで、その解決の糸口を探っているようであった。
コーディネーター役の平野さんは、デザイン開発を核に各種の商品開発、市場開発のコンサルティングを手がけている方だが、当日紹介された事例をひとつ紹介しよう。
コダックは日本ではフイルムメーカーとしてはなじみ深いものの、映画用のプロセッシング機器やカメラをつくっていることはあまり知られていない。アメリカでは四〇%ほどのカメラのシェアを持っているにも関わらず、日本ではわずか数%。そこで相談を受けた平野さんらは、コダックのカメラのシェア拡大のための戦略を立てたのである。
 その戦略のもと日本の市場に投入された第一号が、昨年七月に発売されたDC4800というデジタルカメラ(Gマーク受賞)。三・一メガの解像度、三倍の光学レンズを使ったマニア向けのカメラで、同レベルの輸入カメラのなかでは技術的には上のクラス。銀塩の高級コンパクトカメラの仕様や操作性を持っているため、九万九八〇〇円に設定された価格は高く感じられないらしい。 その戦略のもと日本の市場に投入された第一号が、昨年七月に発売されたDC4800というデジタルカメラ(Gマーク受賞)。三・一メガの解像度、三倍の光学レンズを使ったマニア向けのカメラで、同レベルの輸入カメラのなかでは技術的には上のクラス。銀塩の高級コンパクトカメラの仕様や操作性を持っているため、九万九八〇〇円に設定された価格は高く感じられないらしい。
その二カ月後に、今度はその小型版としてDC3800を発売。従来、日本のカメラ市場ではコダックは五〇位以内に入ったことがなかったが、この機種は他メーカーの同型機種と上位争いをするまでになった。
コンサルティングに携わった平野さんは、プロモーションの背景を以下のように説明した。
「われわれはシェア拡大のために、一〇年間の戦略を立てました。そして最初に出したのがDC4800です。これはスター商品として開発しました。マニア向けのカメラですが、技術と高級感を市場に見せて、買いたい人は買ってください、という姿勢でいる。そうすると『コダックは変わったね。フイルムだけじゃなく、技術も高級感もあるいいカメラつくるじゃない』と企業に対する認識が変わってくる。その上で量産品の小型版を出すと、コダックに対する市場環境が変わりつつある時ですから、注目を集めて売れる。新商品は売り出すタイミングで、売れ方が変わりますから、われわれは初めからこれを狙っていました」 |